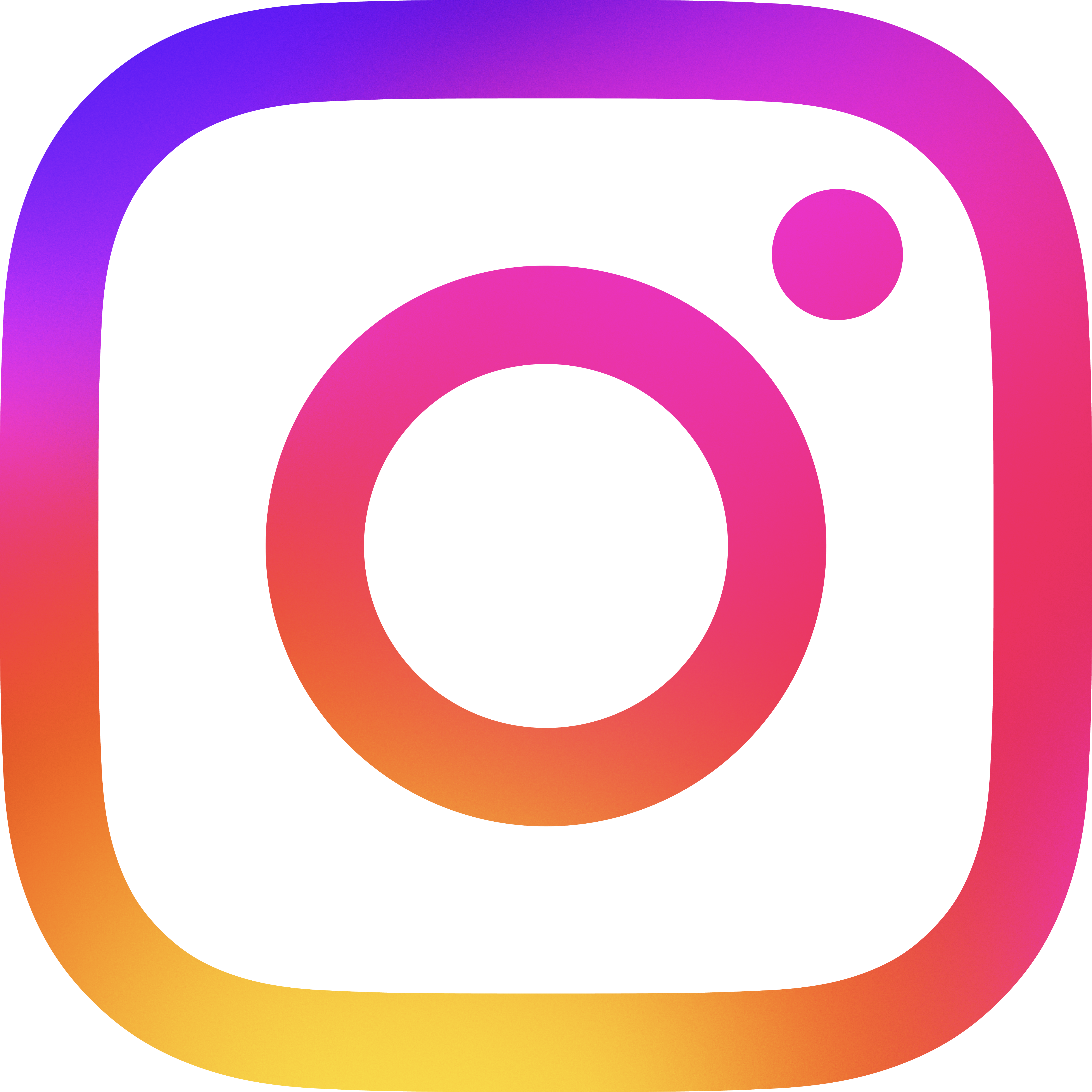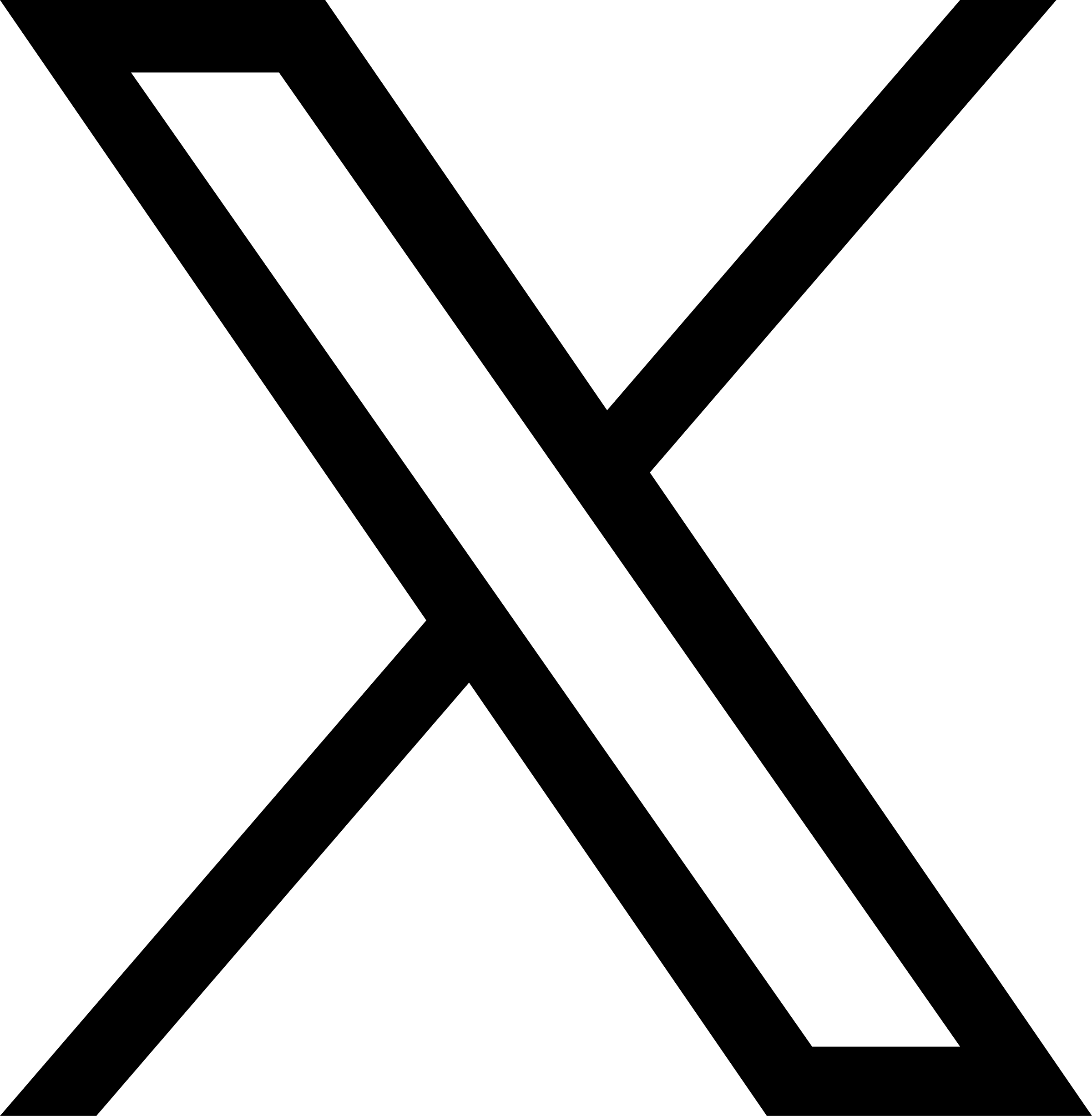FAQ(WEBサポート)
修正(乾燥状態)
Q乾燥後、リングが割れてしまった。どうすれば良いか?
リング状の場合
【1】割れたパーツを確認します
- 割れたそれぞれのパーツが元の形のどの部分にあてはまるか、上下左右など確認し位置をきめます。
【2】木芯棒に付箋紙をつけます
- 制作していた時と同じ号数に合わせた付箋紙をまきつけます。
(付箋紙の中心に鉛筆などで中心線を書いておくと作品中心の目安になります)
【3】割れたパーツを組み合わせます
- 割れ口に湿らせた筆等で水分を少し加えます。
→乾燥したままの状態の粘土ですと、次に盛り付ける修正用のペースト・シリンジタイプ等がはがれやすいためです。 -
水分が浸透したら【2】の付箋紙の上で、ペースト・シリンジタイプ等を、割れ口にたっぷりと塗りパーツを接着します。ここでは乾燥させずに、一気に残りのパーツを接着していきます。輪の状態になったところで乾燥させます。乾燥後、割れ口だった部分が目減りしていたら、上から再度ペースト等で補強し完全に乾燥させます。
→この時の修正に使うペーストはパテ状くらいのかたさに調節すると修正しやすいです。
→割れ口が完全に覆いかぶさるように、たっぷりと塗ります。
【4】リングを木芯棒からはずし、内側から割れ口部分をペーストで補強します。この時も【3】の修正と同様に、乾燥後目減りしていたら再度ペーストタイプをたっぷりと塗り、完全乾燥させます。
【5】ヤスリで表面、内側を整えます。
【6】焼成します。
【7】研磨など仕上げをします。
Q乾燥後、プレート状の作品が割れてしまった。どうすれば良いか?
プレート状の場合
【1】割れたパーツを確認します
- 割れたそれぞれのパーツが元の形のどの部分にあてはまるか、上下左右など確認し位置をきめます。
【2】割れたパーツを組み合わせます
- 割れ口に湿らせた筆等で水分を少し加えます。
→乾燥したままの状態の粘土ですと、次に塗る修正用のペースト・シリンジタイプ等がはがれやすいためです。 - 水分が浸透したらペースト・シリンジタイプ等を、割れ口にたっぷりと塗りパーツを接着し乾燥させます。乾燥後、割れ口だった部分が目減りしていたら上から再度ペーストタイプ等で補強し完全に乾燥させます。
→この時の修正に使うペーストタイプはパテ状くらいのかたさに調節すると修正しやすいです。
→割れ口が完全に覆いかぶさるようにたっぷりと塗ります。
→クッキングシートを作品の大きさより一回りくらい大きめにカットし、その上で作業すると修正しやすいです。
【3】裏側から割れ口部分をペーストタイプで補強します。この時も【2】の修正と同様に、乾燥後目減りしていたら、再度ペーストタイプをたっぷりと塗り完全乾燥させます。
【4】ヤスリで表面、裏面を整えます。
【5】焼成します。
【6】研磨など仕上げをします。
Q乾燥品同士を接着するには?
乾燥品同士を接着させる場合、ペーストタイプで接着することができます。
ペーストタイプをペースト2:水1の割合で良く溶き合わせ、つなげたい部分にたっぷり塗り、接合して下さい。
はみ出したペーストタイプは、乾燥後ヤスリなどで削り、修正して下さい。

Q造形時に粘土タイプの表面にヒビが入ってしまった。どうすれば良いか?
粘土タイプの表面が乾いてくるとヒビ割れます。 こまめに水分を補いながら粘土タイプの形を整えていく事がポイントです。
- 造形中は霧吹き等で粘土タイプの表面を湿らせるか、指先を水でぬらしながら作業をすすめますとヒビ割れが防げます。
- 造形の初期段階でしたら、2重にしたラップフィルムの中に粘土タイプを入れ少量の水を加えてラップフィルムの中でよく練りこみ、元の粘土に戻し再制作します。
Qモールドで造形した粘土に差し丸カンをつける方法は?
差し丸カンを付ける場合は乾燥させてからピンバイスで穴を開け、そこに差し丸カンを差し込んでください。もしくはモールドに薄く油を塗ると乾燥していない状態でも取り出しやすくなります。
修正(焼成後)
Q 焼成後、作品が割れてしまった場合は?
焼成後、作品が割れたのは焼成不足か、もともと作品に深い亀裂が入っていたことが原因です。その時の修正方法をご紹介します。
【1】割れたパーツを確認します
- 割れたそれぞれのパーツが元の形のどの部分にあてはまるか、上下左右など確認し位置をきめます。
【2】割れたパーツを組み合わせます
- クッキングシートを作品より一回り大きくカットして作品の下に敷いて作業します。
→作品を移動させる時などはこのクッキングシートごと移動させます。 - ペーストを、割れ口およびその周辺にたっぷりと塗りパーツを接着し乾燥します。
→割れ口とその周辺を完全に覆いかぶせるように塗るのがポイントです。
【3】乾燥後、割れ口だった部分が目減りしていたら、上から再度ペーストで補強し完全に乾燥させます。
【4】焼成します。
【5】ヤスリで表面を整えます。
→ペーストの余分な部分を削ります。
→ペーストは乾燥状態では剥がれやすいため、焼成後に表面を整えることがポイントです。
【6】研磨など仕上げをします。
Q 焼成後に変形してしまった場合の修正方法は?
焼成後仕上げをする前の白い状態の時に、芯金棒にリングを通してプラスチックハンマー等で軽くたたくと歪みが解消され、真円に近づけられます。
Q 埋め込んでいた合成石が、焼成後外れてしまった。修正方法は?
焼成後はペーストを使って合成石を留め修正します。
合成石が穴に入らない時は合成石と同じ径のドリル刃で穴を開け直してからペーストを使って合成石を留めます。
合成石は角が埋まるくらいしっかりと埋めることがポイントです。
Q 直棒ピアス金具を埋め込んで焼成する際の注意点。
粘土に直棒ピアス金具を埋め込む際、金具の先をヤットコもしくはペンチで曲げておくと、曲げた部分が引っかかって抜けにくくなります。
Q 焼成後のリングにアメジストの小さな石を入れることは可能か?
可能です。焼成後の作品の修正・接着には「ペースト」を使用します。ご使用になられる石が天然石、もしくは合成石によって石留め方法に違いがございますので、それぞれの留め方をご紹介いたします。
※「ペースト」は「アートクレイシルバー」シリーズに使用していただいて結構です。取扱方法・焼成方法(時間・温度)などの詳細に関しましては、製品に付属の取扱説明書をご参照下さい。
【合成石の場合】合成石は熱に強く、アートクレイシルバーと同時焼成が可能です。焼成後の作品に合成石を留める場合はペーストを使用し留めます。
- 方法① 焼成後のリングに合成石と同じ径のドリル刃で穴を開け、ペーストを使用して接着し合成石を留めます。合成石は角が埋まるくらいしっかりと埋めることがポイントです。
- 方法② アートクレイシルバーに合成石を留めたパーツのみを制作し焼成します。ペーストで焼成後のパーツをリングに接着し焼成します。
【天然石の場合】天然石は合成石と違い、焼成しますと変色や割れが生じてしまいます。天然石は焼かずに石留めします。
- 方法① 「アートクレイ専用オリジナル石枠」で天然石を留めます。「アートクレイ専用オリジナル石枠」はアートクレイシルバーに埋めて焼成できるタイプの石枠ですが、焼成後の作品にも使用可能です。焼成後の作品に「アートクレイ専用オリジナル石枠」をペーストで接着し焼成します。焼成後に石を留めるので天然石の使用が可能になります。「アートクレイ専用オリジナル石枠」の取り付け方は「アートクレイシルバーで作る純銀製のアクセサリー基礎ブック(定価1295円)」P58にてご紹介しております。「アートクレイ専用オリジナル石枠」は石のカット・サイズ別に20種類ございます。アートクレイシルバー販売店にて取り扱っておりますが、店舗によっては一部取り扱っていない商品もございますので、もしよろしければアートクレイの材料がネットで買えるショッピングサイト「アートクレイ通販倶楽部」をご利用ください。「アートクレイシルバー総合サイト」https://artclay.co.jpからアクセスいただけます。
- 方法② 純銀リボン線で石枠を作り、アートクレイシルバーと組み合わせ焼成します。そのパーツをペーストで焼成後の作品に接着し再度焼成します。焼成後にその純銀リボン線で天然石を留めます。こちらの方法は、高度な技術を必要としますので慣れていない方には難しいと考えます。 純銀リボン線による石留めの方法は、「アートクレイシルバーで作る純銀のアクセサリー2(定価1295円)」P18~P21にてご紹介しております。
Q SV950の完成品にアートクレイシルバーの粘土を組み合わせる場合の注意点。
SV950とアートクレイシルバーとの組み合わせでしたら可能ですが、その作品の焼成には、電気炉(650℃・30分焼成)を使用します。ガスコンロ・ガスバーナー・アートボックス等での焼成は、あくまでも簡易的な焼成方法ですので、SV950とアートクレイシルバーとの組み合わせ作品に適用できる焼成方法でない事をご了承下さい。
色の違いについてですが、その作品を焼成することにより、SV950表面に黒っぽい酸化膜が生じます。耐水ペーパー、スポンジ研磨材などで酸化膜を除去し、シルバーポリッシュ等で鏡面を出すことで再び銀肌が得られます。
SV950との組み合わせ時に、ご注意していただきたい点がございます。焼成時にSV950ロウ付け箇所(引き輪・バネ部分等)が取れる可能性がありますのでご注意ください。ロウ付け部分を粘土で完全に包み込むことで、ロウ材が減ってしまっても収縮でつなぎとめることが可能です。
注:「SV950」とは一般に市販されている銀製品で、純度が95.0%前後の物を指します。
ここでは、「市販の銀製品にアートクレイシルバーシリーズを組み合わせることで新しい作品に作り上げることは可能か?」 というご質問にお答えしています。
Q 焼成済みのリングの内側にペーストタイプを塗り再度焼成しても問題ないか?
焼成済みのリングサイズを小さくするため、リング内側に「アートクレイシルバーペーストタイプ」を塗り再焼成いたしますと、追加したアートクレイシルバーペーストタイプ部分のみが焼成による収縮で剥がれる事があります。焼成した作品の修正には「アートクレイシルバーペースト」のご使用をお勧めいたします。以下に3方法ご説明させていただきます。
※なお「アートクレイシルバーペースト」の取扱方法・焼成方法(時間・温度)などの詳細に関しましては、製品に付属の取扱説明書をご参照下さい。
□温度管理ができる電気炉で再度焼成する(焼きしめる)方法
- 0.5番程度小さくする場合に有効です。
- 800℃程度の電気炉で10~30分ほど焼成します。
- アートクレイシルバーペーストは使用しません。
□リングの内側に「アートクレイシルバーペースト」を塗り、再焼成する方法
- アートクレイシルバーペーストは焼成後の作品の修正や、焼成したパーツ同士の接着に便利です。
①リングの内側にペーストを塗り、よく乾燥させる。
- 乾燥状態は非常にはがれやすいので周辺につけたペーストは焼成後にヤスリで削り、形を整えてください。
②ペーストの焼成条件で再焼成する。
- 電気炉焼成800℃30分保持をお勧めいたします。
- ガスコンロ焼成の場合は5分保持します。
③アートクレイシルバーペーストで修正した表面の凹凸部分をヤスリや耐水ペーパー(スポンジ研磨材)等で整える。
④研磨する。
- アートクレイシルバーを焼成し研磨したものは、再度焼成することで研磨肌が多少白色になりますが、再度研磨することで光沢が得られます。
□糸鋸でリングの長い部分を切り取り「アートクレイシルバーペースト」でつなぎ再度焼成する方法
①リングを1ヶ所切断して削り、芯金棒に通してサイズを縮めます。
②切断面にアートクレイシルバーペーストを多めに塗りよく乾燥させ、前述の方法②からの手順で再度焼成~研磨までの作業を行います。
Q SV925のリングの片側をカットしたいが粘土で修正は可能か?
可能です。修正方法にはペーストを使用します。方法としては
① カットした面に竹串などでペーストを塗布します。(ペーストはやや多めに盛り付ける方が焼成後、接合面をきれいに仕上げることが出来ます。)
② 接着後ペーストが個化するまで十分乾燥します。(ドライヤーでの強制乾燥の場合は30分間、自然乾燥の場合は24時間が目安です。十分に乾燥チェックを行なって下さい。乾燥が不充分な状態で焼成するとペーストが泡立ち、接合強度が弱まります。)
③ 焼成後、多めに盛り付けたペーストの部分を中目ヤスリで削り整え、スポンジ研磨材、もしくは磨きヘラで磨きます。(セッティング・焼成方法はA.C.Sを焼成する方法と同じです。)
注:「SV925」とは一般に市販されている銀製品で、純度が92.5%前後の物を指します。
ここでは、「市販のシルバーリングをサイズ修正する等の際にアートクレイシルバーシリーズでの修正は可能か?」というご質問にお答えしています。
Q シリンジタイプで制作したリングのサイズを小さくしたい。
再焼成することで0.5番程度は小さくできます。その際、800℃程度の電気炉で10~30分ほど焼成してください。この条件で収縮があまり見られないようでしたら、粘土をリングの内側に足して小さくします。シリンジタイプの線の隙間が埋まりすぎないように固めのペーストタイプか粘土タイプを部分的にはりつけ、滑らかにして焼成します。
Q 焼成後のリングのサイズは変えられるか?
サイズが小さい場合は芯金に通して木槌で少しずつたたいてのばします。大きい場合は再度焼成(870℃設定30分保持)します。もしくは糸鋸で長い部分を切り取りペーストでつなぎ再度焼成するか、リングの内側に粘土をはりつけ再度焼成します。
Q 焼成以外に盛り付けた樹脂を剥がすことは可能か?
工業用のアセトンという商品があるのですが、アセトンをコットンに染み込ませ、剥がしたい樹脂の上に置きます。そしてアルミホイルで巻き30分程そのままにして下さい。そうすると簡単に剥がす事が出来ます。
 HOME
HOME アートクレイシルバー
アートクレイシルバー 商品紹介・販売店
商品紹介・販売店 全国の教室
全国の教室 制作レシピ
制作レシピ FAQ
FAQ