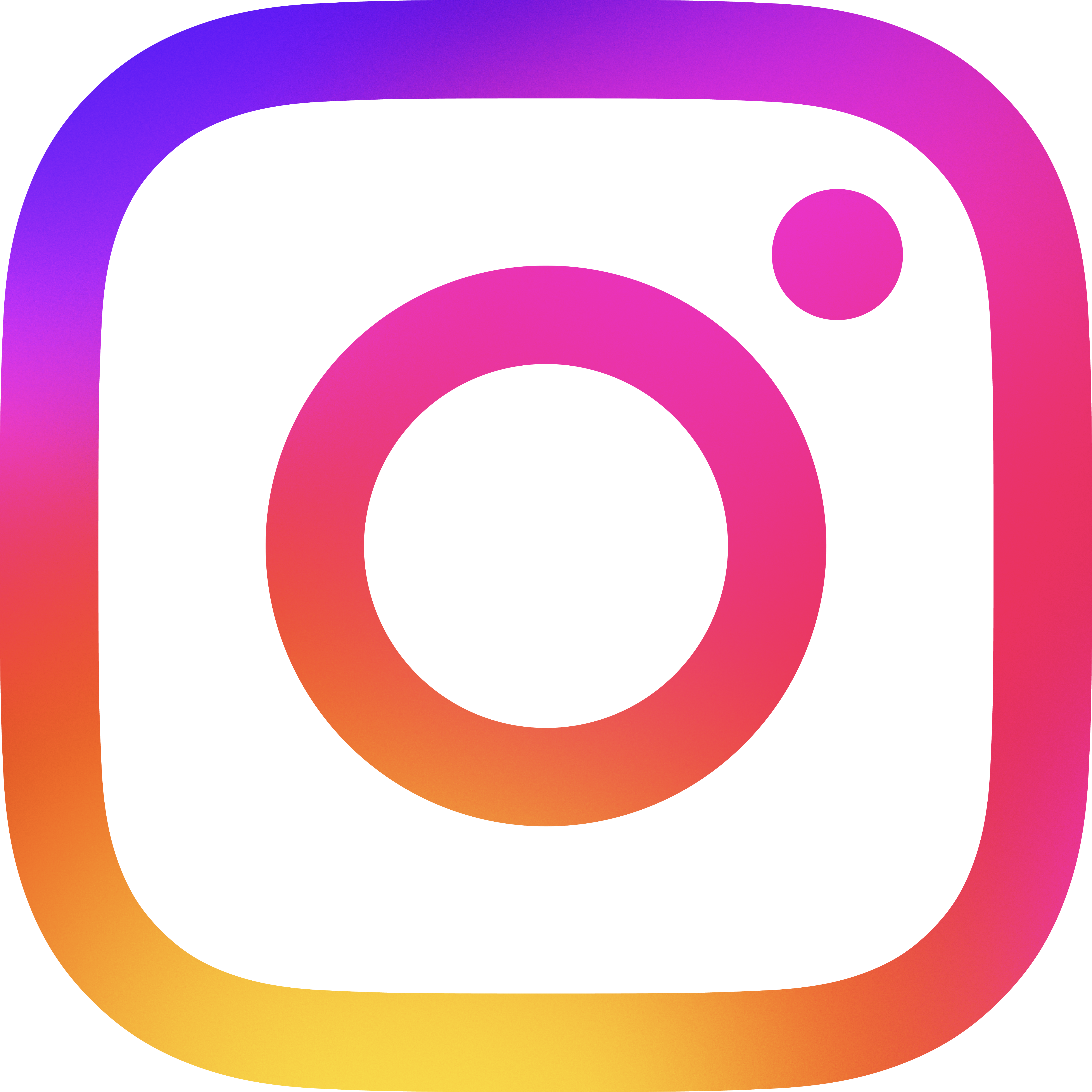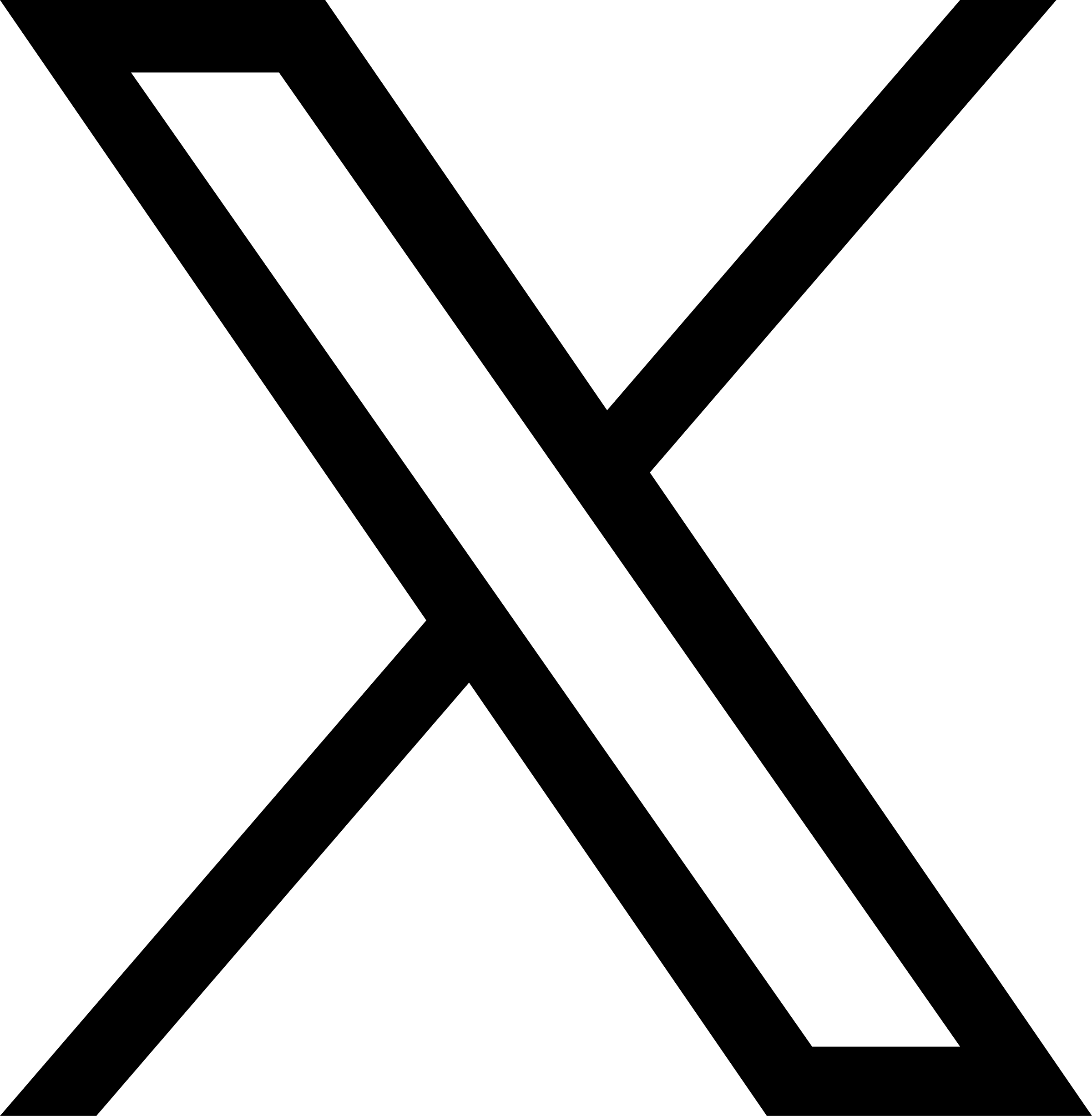FAQ(WEBサポート)
造形
Qリング制作で、粘土がうまく木芯棒(付箋紙)に巻き付かない時は?
木芯棒に粘土を巻き付ける際に、粘土表面全体を水で湿らせてから巻き付けます。そうすることで粘土が付箋紙にはり付き巻きやすくなりますし、粘土表面のヒビ割れも防げます。

Qどの位まで細いもの、薄いものが作れるか?
作品のデザインにもよりますが、シリンジタイプで押し出した線で、ある程度の強度を持つためには最低でも3層重ねる事が必要です。プレート状のものですと、最低でも厚みは0.5mm程度は必要になります。力の加わるアイテムの作品(リングやバングルなど)を作る時には1mm以上の厚みをつけたほうが良いです。
Qペーストタイプの基本的な取扱いは?
ペーストタイプは粘土タイプに一定量の水を加えて練り込み、液状にしたものです。
使い方として
- 粘土タイプの乾燥品同士の接着
- 粘土タイプのひび割れなどの修正
- 粘土タイプに模様を描く(ドローイング)
などに使用します。
扱い方は筆にとり、絵の具を塗るような感覚で使用します。基本的に水で溶いて使用します(ペースト2:水1の割合)作業内容により、水を加えてやわらかく溶いたり、少し乾かせてパテ状くらいのかたさにするなど、作業しやすいかたさに調節すると良いです。
 乾燥品同士の接着
乾燥品同士の接着 ひび割れなどの修正
ひび割れなどの修正 模様を描く
模様を描く
(ドローイング)
Q作品に文字を入れるにはどうしたら良いか?
作品に文字を入れるには2つの方法があります。

粘土状態の時に彫る方法
粘土タイプが柔らかいうちに、先の尖った物でひっかくようにして彫っていきます。簡単に彫れて間違いの修正などもしやすい反面、彫る際にバリが出てしまうためシャープな文字は表現しにくくなってしまいます。
乾燥状態の時に彫る方法
乾燥させた粘土タイプに鉛筆などで下書きをし、先の尖ったもので削っていきます。この方法は、シャープな文字が彫り込めます。リングの内側に関しても、この方法で同様に彫り込めます。
乾燥品に文字を彫る時にはスパチュラという道具を使用すると便利です。スパチュラの中にも色々な種類があり、その中でも先端が細くL字型に曲がったもので彫るとよいでしょう。文字をキレイに彫るコツは、鉛筆などで下書きをして全体のバランスを見てから彫ることです。深く彫りたい時は一気に彫り込まず、少しずつ削っていくとキレイに彫ることができます。また、細い文字を彫ろうとして粘土が欠けてしまうときは彫る面を軽く湿らせると(ウェットティッシュなどで軽くなでるなど)彫りやすくなります。ただし、表面を湿らせた場合、焼成前に完全に乾燥させてから焼成を行って下さい。
※ニードルの先に水分が残ったまま放置しますと錆びる可能性がありますので使用後は必ず水気を拭き取って保管してください。
Q造形時に粘土タイプの表面にヒビが入ってしまった場合は?
粘土タイプの表面が乾いてくるとヒビ割れます。 こまめに水分を補いながら粘土タイプの形を整えていくことがポイントです。
- 造形中は霧吹き等で粘土タイプの表面を湿らせる、または指先を水でぬらしながら作業をすすめますとヒビ割れが防げます。
- 造形の初期段階でしたら、2重にしたラップフィルムの中に粘土タイプを入れ少量の水を加えてラップフィルムの中でよく練りこみ、元の粘土に戻し再制作します。
Q銀粘土を練る時に手につきやすいが、改善方法は?
粘土タイプを練る時は、ラップフィルムを使用すると粘土タイプが手につきません。
2重にしたラップの中央に粘土タイプを置きラップフィルムをたたみ粘土タイプをラップフィルムで挟んだ状態にします。その上から指で押さえて粘土タイプをのばし、のびたらラップフィルムを開いて粘土タイプを折たたみ、再度ラップフィルムの上から押さえてのばしていく。この繰り返しです。
粘土タイプが乾いているようであれば水を少量ずつ加えながら押しのばしていきます。
水を加えすぎると、粘土タイプの表面がペースト状になってきますのでご注意ください。
Qリングの輪をつくる時にヒビが入りやすいが、どうすれば良いか?
リングの輪をつくる時にヒビが入るのは、粘土タイプの表面上が乾いていることが原因です。
※リングの制作にかぎらず、粘土タイプの形を曲げたり、ひねったりする等、形を動かす場合は粘土タイプの表面を水で湿らせます。乾いていた部分に水が浸透してからその作業をするとヒビ割れを防げます。
Qリングのつなぎ目をきれいにするには?
少し太めのリングを作る場合
粘土を木芯棒のサイズ1周分よりも少し短めのひも状に伸ばします。木芯棒に巻きつける時、巻き始めを付箋紙になすりつけるように少し指で押しつけます。
残りも指で押し伸ばしながら巻きつけ、太さと長さを出していきます。巻き終わりは、巻き始めの上に重ねて指でなじませます。(つなぎ目部分の粘土を指でつまんで完全になじませるとよりしっかりします。)
乾燥させて木芯棒から取り外し、つなぎ目に隙間があれば、ペーストタイプで埋めて再度乾燥させ、ヤスリ等で形を整えます。
細めのひも状リングを作る場合
粘土を木芯棒のサイズちょうど1周分よりも少し長めに伸ばします。
巻き終わりは、巻き始めの上にのるように重ねて巻きつけます。
継ぎ目は、重ねた2本の粘土をいっぺんに上からカッターで切り、余分な端の部分(巻き始めと巻き終わり)を取リ去り、2本の粘土の断面に少量のペーストタイプをつけ、断面どうしが面でくっつくように指で両側の粘土を少し押します。
乾燥させて、木芯棒からはずし、つなぎ目に隙間があれば、ペーストタイプで埋めて再度乾燥させ、ヤスリ等で整えます。
※ リングを巻き付けた際、余分な粘土タイプはカッターでカットし、水をつけた指でこすってそれぞれをなじませます。
つなぎ目部分が分からないようになじませるのがポイントです。
(下図参照)
 余分な粘土を斜めにカット
余分な粘土を斜めにカット 水をつけた指でなじませる
水をつけた指でなじませる
Q銀粘土を平板状にのばすには?
粘土を棒状にのばしてから、クッキングシートではさみます。
その粘土の両側に厚紙等(希望する厚さの物)を置きローラー等を転がしますと、均一な厚みの帯状にのばせます。
余分な粘土タイプはカッターでカットします。
この時にテレホンカード等のカードを粘土タイプに押し当てカットすると便利です。

Qアートクレイシルバーとアートクレイゴールド/K22を組み合わせることは可能か?
焼成温度がそれぞれ異なりますので粘土状態同士を組み合わせて焼成することはできません。
組み合わせる場合は、はじめにアートクレイゴールド/K22のみを焼成し(990℃60分保持)、焼成した22金粘土はアートクレイシルバーの収縮で留めるように施し再度焼成します。
Q木芯棒より大きいサイズのリングを制作する場合は?
木芯棒の形が延長するように、紙を木芯棒に添わせて巻きます。
その筒状に巻いた紙の中に芯になる物(紙を硬くロール状にした物など)を詰め込み木芯棒の代用とします。
Qアートクレイでバングルを作ることは可能か?
制作する事が出来ます。ただしアートクレイシルバーは焼成後、純銀になりますので、金属的に柔らかい性質があります。 また、バングルのように円状になっていない形状のものを制作する場合、アートクレイだけで制作しますと、強度が足りなくなり、付けはずしで負担がかかって、割れてしまう場合があります。
制作上の注意点として、
- アートクレイシルバーは焼成後、約10%程度収縮します。収縮を考慮して大きめに制作して下さい。
- 強度を持たせるために十分な厚みのあるものを制作して下さい。
- 通常アートクレイシルバーの制作では、フリーサイズのデザイン(輪になっていない形状のもの)は、お勧めしておりません。ただし、バングルの場合、芯に充分な太さの純銀線を入れることで、強度をもたせ、着用に耐えられるようにしてください。
また、制作のコツとして、
純銀線で芯を作るときのポイント
- 純銀線は、直径2mm以上のものを使用します。
- 手首に純銀線を巻きつけてサイズを測る際、粘土を巻きつけるときの厚みを考えて、ある程度ゆとりをもって芯を作ります。
- 芯の形を手首にそうように、きれいな楕円状に形を整えます。
粘土を巻きつけるときのポイント
- 純銀線の両端を出して制作します。純銀線の両端を出しておくと、両端から中央に向かって収縮しやすくなるため、バングルの中央が焼成によって割れることがなくなります。
- 純銀線を粘土タイプで包み込む際は、粘土タイプをひも状にのばし、純銀線の内側から押し付けます。純銀線がひも状の中央部分にくれば、純銀線の上ではみだした粘土をつまむようにして閉じます。
- 純銀線がバングルの外側寄りにならないように注意して下さい。焼成によって、割れやすくなります。
作品例
※各作品をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。
Q甲丸タイプのリングは造形時、どのくらい大きめに作れば良いか?
甲丸タイプの制作時の号数についてですが、収縮率はリングの形、サイズ、使用する粘土の量により違います。基本的に幅が広いもの、粘土量が多いものは収縮も大きいとお考え下さい。
逆に幅が細いもの、粘土量が少ないものは逆に収縮も小さいです。
例えばひも状リングで太さ(直径)が3ミリほどのリングは3号大きく造形します。
平打ちリングで太さ1cm以上、厚さ1.5ミリ程のリングは約4号大きく造形します。
この両方より太さと厚みがあるリングでしたら、5号大きく造形してください。
焼成後は心金棒に通し、リングを回しながらプラスチックハンマーで軽く叩くとかたちのゆがみを直し、サイズを0.5号程度大きく直すことも出来ます。
リングが大きすぎた場合は再度焼成し、焼きしめることで縮めることができます。
他の注意点としましては、乾燥時に表面をなめらかに整える際、内側を削りすぎると号数も変わってしまうので気を付けて作業してください。
Qトゥーリングを制作したいが、どうすれば良いか?
トゥーリングは、足の指の太さに対応できるように通常、開閉タイプになっています。
しかしアートクレイで作る場合、開閉タイプにしてしまうとポーラス状なので使用しているうちに、割れてしまいます。
制作する時は、円になるように制作して下さい。
トゥーリングは粘土の使用量が少ないため、収縮が少なくなります。
1.5号~2号UPを目安に制作して下さい。
また、開閉タイプのリングやソフトワイヤータイプなど市販のものを使って、リングトップのみ制作する方法があります。その場合は、トップ部分の裏に丸カンや、だるまカンなどを埋め込んでおき、最後にリング本体とテグスで結びます。
制作は、トップのみですが、つけごごちがよいので、好みによって制作方法をお選び下さい。
Qピアスを作る場合の注意点を教えてほしい。
直棒ピアスを使用する場合は、粘土が柔らかいうちに直棒ピアスのパーツを粘土に差し込んで下さい。
その際、埋め込む部分にヤスリなどで溝をつけておく、もしくはヤットコなどで金具の先をLの字の曲げておくと金具が抜けにくくなります。
埋め込む深さは、1~2mm程度です。向きは、キャッチを止める溝のないほうを埋めて下さい。
あまりパーツのトップにボリュームがあるデザインだと、直棒ピアス金具を埋め込む深さが必要になってきてしまうため、あまり大きなものには、むいていません。
焼成は、650℃30分で行なって下さい。直棒ピアス金具は、SV925なので低温での焼成をお勧めします。
酸化膜が出来た場合は耐水ペーパーやステンレスブラシなどで酸化膜を取り除いて下さい。
Q合成石とアートクレイシルバーの組み合わせ方法は?
合成石の留め方について、直接合成石を留めて焼成し粘土の収縮によって石留する方法と、石枠を粘土に埋め込み焼成後に合成石を留める方法をご紹介いたします。
直接合成石を留めて焼成する方法
- 合成石の直径に合わせたドリル刃で、乾燥後の作品に石が完全に埋まる深さの穴をあけます。
- 穴の中に少量のアートクレイシルバーペーストタイプをつけ石の幅が一番出っ張っている部分が埋まるように石を入れます。
- ペーストが乾燥したら焼成します。
石枠を使い留める方法
粘土造形後、粘土がやわらかいうちに、合成石の直径に合わせたアートクレイ専用オリジナル石枠を埋め込みます。
この時、石枠の足がしっかり埋まるようにしてください。
また、乾燥した土台にペーストで石枠をとりつけることもできます。
焼成し研磨した後に石を留めます。石枠に石を入れ、ピンセットの柄を使って石枠の爪を倒します。爪は対角の順番に少しずつ倒します。
今回は、合成石をお使いになるということですので、制作するデザインによって石留めの方法をお選びいただけます。
天然石は、焼成すると割れることがありますので、組み合わせる場合は、焼成後に石留めをする方法が適しています。
合成石、天然石の特性に合った留め方をされると良いでしょう。
Q合成石などを埋める場合の注意点は?
合成石を作品に埋める場合、合成石の真下の土台は穴を貫通させていることが望ましいです。
これは合成石に対する光の透過を良くするためであり、粘土の収縮のためではありません。
甲丸リングの場合も同様で、作品のデザイン・構造上問題がなければ石の裏側は穴を開けておくと良いでしょう。
天然石をリボン線で留める場合は、使用する天然石の透明度によって石の裏側の粘土に穴を貫通させるか決めます。
例えば、琥珀、ピンククオーツ、ルチルクオーツなど、光を透過させる石は裏に穴を開けると石がたいへん美しく見えます。
トルコ石、マラカイト、マグネサイトなどは穴をあける必要はありません。
合成石も宝石も、透明度の高い石は、石の表側だけでなく裏側からも光を取り入れた方がより輝いて美しく見えます。
石の美しさと価値が最大限に惹き出されていますと、その作品の価値や完成度も高まると思います。
QアートクレイシルバーとSV925と組み合わせる際の注意点は?
一口にSV925の金具といっても、その構造と機能は様々です。
SV925地金のバネ性を利用した金具(スクリップイヤリングなど)やロウ付けで組み立てられた金具(チェーンの引き輪など)などは650℃での焼成でもその機能を失ってしまうことがあります。出来るだけ単純な構造の金具(ピアスのポストなど)で単一の部品からできている金具が同時焼成に向いています。
また、低温での焼成でも酸化膜はできますので金具全体がグレーに変色します。ステンレスブラシなどで磨いて銀の肌を出してください。
Qアートクレイゴールドペースを使用する際の注意点は?
焼成品にはつかないので乾燥品に塗って下さい。
焼成はノーマルの粘土タイプの焼成温度と同じで、800℃30分か870℃10分で行なって下さい。
ゴールドペーストは盛り付けすぎるとシルバーとの収縮率が違い、うまく焼成できないので注意して下さい。
Q現在使用している銀製品につけることはできないか?
地金のものに巻きつけるようにし、収縮を利用して固定することは可能です。
焼成によって地金(SV925・K18など)が黒く変色し、表面だけでなくその金属自体まで酸化させるためにもろくなるおそれがあります。
この場合はアートクレイシルバー650を使用し、低温での焼成をおすすめします。
Qモールドを使った制作上のポイントを知りたい。
- シリコンモールドできれいに型取りをするためには、詰める型のシルエットに合わせて粘土をある程度形作っておくことが大切です。粘土を型に入れたら、中心から外に向かって指でしっかりと押し、型と粘土の間の隙間をなくします。
外側から中心に向かって押すと、型がよれたり、空気が抜けなくなってしまいますのでご注意ください。
また、あらかじめモールドの表面にオイル(食用油)を塗っておくと詰めた粘土が取り外し易くなります。
塗りすぎてしまったオイルはティッシュペーパーなどで軽く拭き取りましょう。
モールドで形をとった粘土はよく乾燥させてから取り外すと良いようです。モールドによる工程
 粘土を詰めます。
粘土を詰めます。
この時、型にオイルを塗っておくと後で粘土が取り外しやすくなります。 型の枠からはみ出た分は切り取ります。
型の枠からはみ出た分は切り取ります。 ドライヤーで乾燥します。
ドライヤーで乾燥します。
完全に乾燥しないと取り外す時に割れてしまうことがありますのでご注意。 乾燥終了。
乾燥終了。
取り外す時に割ってしまわないように注意しましょう。 乾燥品。
乾燥品。
ここで模様や文字の彫り込み、丸カンなどの金具の取り付けをします。 焼成をし、磨き上げ、完成です。
焼成をし、磨き上げ、完成です。
- 取り外した粘土にスパチュラやニードルで模様や文字を彫り込む場合は、完全に乾かしきった後か、ウェットティッシュで表面を少し湿らせてから彫り込みます。
彫り込むときは一気に強く削るのではなく、少しずつ繰り返し削るようにするときれいに彫り込めます。
【参照】作品に文字を入れるにはどうしたら良いのですか? - 丸カンを差し込むには、完全に乾かしたものにピンバイスで穴を開けて差し込むか、型を取って乾燥させていない粘土状態のうちの作品に差し込むと良いでしょう。
注意:モールドで型を取った粘土に限りませんが、乾燥が不十分なものに細工をしようとすると砕けたりヒビが入ってしまう可能性が高くなります。
必ず、乾燥チェックをしっかりしてから細工をしていきましょう。
完全に乾燥したものでも、強い力が加わってしまうと欠けてしまいますのでご注意ください。
造形段階のものは水分が不足するとヒビが入ってしまい、乾燥や焼成をしたときに割れてしまう原因ともなりますので、表面に水分を足しながら作業を行って下さい。
Qアートクレイシルバーとガラスを同時に焼成することは可能か?
アートクレイシルバーとガラスを同時に焼成することは可能です。
ガラスとアートクレイを組み合わせる場合、ガラスをフュージング(ガラス同士を溶け合わせて、溶着させること)してから使います。ガラスを室温から電気炉に入れ、700℃~870℃の温度でフュージングします。その後、870℃に達した電気炉の扉を開け550℃位まで温度を下げます。550℃になったら電気炉の扉を閉めて炉内温度が室温になるまでゆっくり除冷します。
その後、アートクレイシルバーと組み合わせて焼成します。フュージングしたガラスのかたちを変えずにアートクレイシルバーの収縮により、ガラスと組み合わせる場合、650℃ 30分保持した後、550℃まで電気炉の扉を開けて急冷し、その後扉を閉めて室温までゆっくり除冷します。
参考書籍:アートクレイシルバーで作る銀とガラスのアクセサリー(日本ヴォーグ社)
お作りになりたい形やイメージによって、制作方法はことなりますが、共通して ガラスと組み合わせる際に注意しなくてはいけないことが数点あります。
- ガラス単体での焼成では変色しなくても、ガラスによっては銀と組み合わせた場合に黄変する場合があります。
- ガラスとアートクレイシルバーの相性が悪いと、割れてしまうことがあります。膨張係数が異なるガラス同士をフュージングすると歪が生じ、割れてしまいます。膨張係数90のガラスを使用されると良いでしょう。
- ガラスは、急激な温度変化を嫌いますので、常温から徐々に温度を上げ下げします。
そのために焼成は電気炉で行ってください。 ガラスは、高温で焼成しますと変形しますので、形を変えたくない場合は アートクレイシルバーを使用し、650℃で焼成しましょう。
上記の点に注意していただき、まずテストとしてアートクレイシルバーと使用されるガラスの溶け具合をテストしてから、作品制作されることをお勧めいたします。
Q全部使い切ったシリンジの中に、ペーストタイプを入れて使用できるか?
シリンジタイプとペーストタイプでは粘土に含まれる水分量が違います。
ペーストタイプはシリンジタイプよりも水分が多く含まれているので、お勧めは出来ません。
Qリングサイズシートの使い方を知りたい。
まず、リングサイズシートの端の切り取り部分をハサミでカットします。
このカットした部分からの距離がリングの円周の長さとなります。
アートクレイシルバーは焼成によって収縮しますので、制作するときは作品の収縮を考えたサイズに設定します。
例えば完成サイズが12号の場合、制作は15号で設定します。
※アートクレイシルバーは長さで約8~9%収縮しますが、リングサイズで見た場合の収縮は、形状やサイズ、使用する粘土タイプの量によって異なります。
基本的にサイズや使用粘土量が大きくなるほど収縮は大きく、サイズが小さいほど収縮も小さくなります。
Q保存していた粘土タイプが乾燥してしまった場合は?
また、乾燥してしまった粘土タイプに水分を加えて練ってもうまく混ざらない。何か良い方法はないか?
乾燥してしまった粘土を、元の粘土のような固さに戻す方法を紹介します。
- 小さなゴミ等の不純物がないか確認し、あれば取り除きます。
- ラップを3~4枚重ね、その中央に乾燥した粘土を置き、水を加えます。
→この時の水分はその乾燥した粘土体積の約4分の1くらいです。
→水を加えすぎると粘土がペースト状になるので注意します。 - 粘土が中央にくるように、空気をぬきながらラップをピッタリくるみます。
- ウエットティッシュ2~3枚で(3)を包み、フィルムケース等の密閉容器にいれます。(アートクレイシルバー粘土タイプのチャック付きアルミパックも利用できます。)
- (4)を一晩ねかし、ラップフィルムの上から、ローラーなどでかたまりをつぶします。
ラップフィルムを開け、中の粘土をまとめ、再度ラップフィルムの上からローラーなどでかたまりをつぶします。
これを繰り返し、粘土が柔らかくなったらラップフィルムの中で良く揉み込みます。
それでもこごりが残るようであれば水を加え一晩ねかせてから、再度この作業を行って下さい。
Q天然石とアートクレイシルバーの組み合わせ方法を知りたい。
天然石は同時焼成することが出来ません。
天然石をアートクレイと同時焼成してしまうと、割れてしまったり変色してしまう恐れがあります。どうしても同時に焼成したい場合はまず石のみで焼成を行ない割れや変色が無いかを確認して下さい。
天然石を使用する場合はA.C専用の石留め枠を使用するか、純銀リボン線を使用して石留めを行なって下さい。
純銀リボン線で石枠を作り、焼成後にその純銀リボン線で天然石に留める方法
こちらの方法は、高度な技術を必要としますので慣れていない方には難しいと考えます。
アートクレイ専用オリジナル石枠で天然石を留める方法
アートクレイに埋めて焼成できるタイプの石枠「アートクレイ専用オリジナル石枠」を使用しますと、焼成後に石を留めるので天然石の使用が可能になります。
※「アートクレイ専用オリジナル石枠」は石のカット・サイズ別に20種類ございます。
アートクレイシルバー販売店にて取り扱っておりますが、店舗によっては一部取り扱っていない商品もございますので、もしよろしければ当社の通信販売をご利用ください
Qアートクレイシルバーで焼印を作れるか?
結論から申し上げますと、焼印を作る事は可能です。
一般的に焼印は鉄を使用しています。
理由として鉄の融点は約1530℃なのでエアバーナーなどでは融解する事がないためです。
しかし純銀の融点は約960℃です。そのため使用する際には加熱温度に注意して下さい。
目安として焼印として使用する部位(先端部分)をバーナー等で熱を加えた際、オレンジ色に発光し始めます。
それ以上熱してしまうと融点を越え融解してしまいます。
またオレンジに発光しているアートクレイシルバーを布のような燃えやすい素材に焼き当ててしまうと出火の原因になる可能性がありますので十分ご注意下さい。
Q一度乾燥したアートクレイシルバーを再び元の粘土状態に戻すことは可能か?また、焼成したものは可能か?
一定の水量につけておくことにより、水を吸収して戻ります。早く戻したい場合は細かく砕き、水を加えます。
途中でよく練るようにすると粘土状態に戻ります。
焼成後は、バインダー成分が燃焼して銀粉体が焼結するので戻りません。
Q焼いたもの同士を接着するには?
焼成したもの同士を接着するには「アートクレイシルバー油性ペースト」を利用します。
アートクレイシルバー油性ペーストの使い方といたしましては、接着面とその周辺に多めに塗ってからくっつけ、よく乾燥させてから焼成してください。乾燥状態は非常にはがれやすいので、周辺につけた油性ペーストは焼成後にヤスリで削り、形を整えてください。
Qアートクレイシルバーに水を足してペーストとして使えるか?
同じように使えます。焼成条件も650℃、30分のままです。
 HOME
HOME アートクレイシルバー
アートクレイシルバー 商品紹介・販売店
商品紹介・販売店 全国の教室
全国の教室 制作レシピ
制作レシピ FAQ
FAQ